
Sunohara Blog
Sunohara Blog
コンシェルジュ春原ブログ
こんにちは、Blue styleコンシェルジュの春原です。
唐突ですが、みなさん旅行は好きですか?
私も学生の頃はリュック片手に海外へ、と今思えば...勢いだけで飛び出してました。
世界遺産、的な遺跡を見て回っていたのですが、
いまだに日本を飛び出したくなる衝動がたまにあります✈
電車、車、飛行機と、
いまはどこへでも行ける便利な時代ですが、
江戸時代はどうだったの?というのが今回のお話です。
静岡で研修があったので、お休みのタイミングに、
へ行ってきました。

美術館のタイトルにある歌川広重は「東海道五十三次」が有名な浮世絵師です。

諸国漫遊~というと、すごく自由なタイトルですが、
当時の民衆は自由な移動が制限されていました。
関所を越えるには通行手形が必要で、
「そうだ、京都行こう」も簡単に出来なかったわけですね。
浮世絵はそんな庶民にとって、旅への想いを馳せるガイドブックだったようです。
うまく説明できないので、美術館の「浮世絵とは」より説明抜粋ご紹介です。
「浮世」とは人々が生きているこの世の中を指しています。
この「浮世」を描いたものである浮世絵には、その当時に生きていた人々の暮らしや文化、流行など、
彼らが興味を持ったありとあらゆる物事が描かれています。
館内を拝観していて印象に残ったのは、
「木曽海道六十九次」です。
江戸(日本橋)から京都(三条大橋)を結ぶ、
69ヶ所の中山道の宿場が描かれています。
(東海道五十三次が静岡や愛知経由の海沿い南ルート、
木曽海道六十九次は長野や岐阜経由の中部横断ルート)
ルートは埼玉県内も含まれていて、
蕨→浦和→大宮→上尾→桶川→鴻巣→熊谷→深谷→本庄
が登場します。
馴染みある地名ばっかりですね。
広重は埼玉の区間を描いていない💦のですが、
その先の望月宿(長野県)で広重の作品がありました。
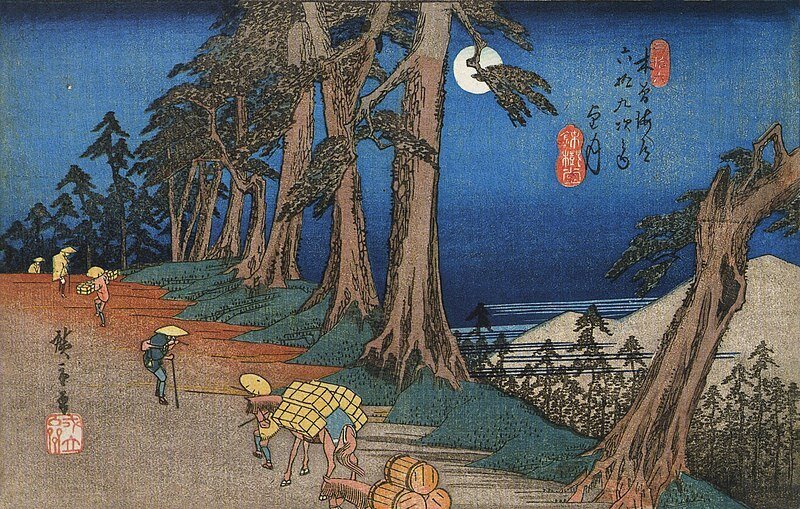
街灯もない当時、
夜は月あかりを頼りに、灯りのともる宿場町へ急ぐ、
そんな当時の風景が印象的でした。
特別展は2025年7月13日まで開催していますので、
機会があれば見に行ってみてください。
次回Blogは美術館隣の由比本陣公園 御幸亭庭園をご紹介します。
